Image by: FASHIONSNAP
「リツコ カリタ(RITSUKO KARITA)」を手掛けるデザイナー 苅田梨都子が、2024年3月に新たな事務所兼店舗となるスペース「S(︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎)」を、東京・四谷三丁目にひっそりとオープンした。バンタンデザイン研究所在学中の2014年に、前身となるブランド「梨凛花〜rinrinka〜」を立ち上げて以来、その物語性の強い独自の世界観と美意識に貫かれたクリエイションによって多くのファンを惹きつけてきた苅田は、今年でデザイナー活動10周年を迎える。衣・食・住すべてに等しく関心と愛情を持ち、デザイナーに留まらず食や映画、美術館にまつわるコラム執筆など多彩な活躍を見せる彼女を訪ねて、完成したばかりのショップを訪問。「デザイナーになろうと思ったことは一度もない」と言葉にする苅田が、数々の偶然と必然を自身の手で手繰り寄せてきた、これまでとこれからの歩みについての話。
■苅田梨都子
1993年岐阜県東白川村出身。母が和裁士で幼少期から手芸が趣味となる。家庭科・衣文化のある高等学校に通った後上京。バンタンデザイン研究所在学中から以前のブランド「梨凛花〜rinrinka〜」の活動を開始。学生時オートクチュールやコレクションブランドのインターンを経験。梨凛花を6年手掛けた後、自身の名前である「RITSUKO KARITA」として活動中。2022年度はブランド活動と並行して週1で母校の講師を務める。趣味が高じて洋画専門チャンネル「ザ・シネマメンバーズ」にて偶数月の20日公開にてコラム執筆中。Hanako webにて「苅田梨都子の東京アート訪問記」連載中。
目次
ADVERTISING

2024年春夏コレクション
Image by: RITSUKO KARITA

2024年春夏コレクション
Image by: RITSUKO KARITA
「デザイナーになろうと思ったことは一度もない」
ー「母が和裁士で幼少期から手芸が趣味」とプロフィールにありました。まずはどんな幼少期を過ごしていたのか教えてください。
私が幼少期の頃、母は家で着物のお直しや仕立てといった和裁士の仕事をしながら、お茶工場でバイトをしたり、村にあった小さなレストランに併設されたパン屋さんで働いたりと、一番やりたい和裁士の仕事をベースにいろいろなことをやっていました。だから、私には母が「就職している」というイメージがなくて、何かを軸にしながらいろいろな「〇〇屋さん」ができるということを近くで見てきました。今思えば仕事や働き方に対するスタンスや価値観にも、自然と影響を受けたと思います。
ー確かに、今の苅田さんの働き方に通ずる部分を感じます。裁縫や手芸も、お母さまの影響で幼い頃からやられていたんですか?
母は和裁だけでなく、趣味でビーズアクセサリーなども作ったり、よく私と双子の妹に色違いでお揃いの洋服を作ってくれたりしたので、「買う」よりも「作る」ほうが身近だったし、縫う姿をいつも近くで見ていたので、ものづくり全般で影響を受けた気がします。子ども時代はとにかく暇すぎたこともあって、デニムパンツを切って自分でリメイクしたり、小学校の夏休みの課題でビーズや編み物で立体の遊園地や動物を作ったり、サンリオのキャラクターのマスコットを50個作ったりと、ずっと縫い物をしていました。
ー今「子ども時代は暇すぎた」とありましたが、ご出身の岐阜県東白川村はどんな場所だったのでしょうか。
駅もコンビニもないし、信号機も黄色の点滅が1つだけしかないような自然豊かな場所で、お茶の産地やヒノキなどの木材の産地としても有名なところです。買い物の楽しみや、新しい文化や人との交流的なものは一切なかったですが、当時はそれが当たり前だと思っていました。そして「自分の手から新しい何かを生み出そう」という発想は、私が都会ではなく、何もない村で過ごしたからこそ生まれたものなのかなというのは、結構自覚している部分でもあります。

ー都市部で生まれ育ったら色々な選択肢や誘惑もありますし、それほど熱心に何かを作ろうという気持ちにはならないかもしれないですね。
小学生の頃はインターネットにもまだ触れていなかったので、テレビや雑誌、ゲーム、漫画以外に何か楽しいことをしようと思うと、何かを作って身につけるというのが、私にとってはその選択肢の一つでした。特に、昔は自分の容姿にすごくコンプレックスがあったので、自分を少しでも可愛く見せるための道具として「服」は身近な存在で。だから、服を自分でリメイクしたり新しく作って身につけることは、自分自身をアップデートして自信をつけることのできる手段と幼い頃から捉えていた気がします。
ー洋服作りの原点には「自分を変えたい」という気持ちが大きかったんですね。
それが一番最初でした。でも、高校生の時に初めて名古屋に洋服の展示会を見に行った際、それまで着ていたような普通の服ではない“コレクション”として作られた服に袖を通したら、まるで魔法にかけられたみたいに新鮮でドキドキした気持ちになったんです。その時に「これを作る人ってすごいな」と感じて、自分もこんなふうに何かを与えられる人になりたい、と思うようになりました。

ーそれがデザイナーになろうと思ったきっかけだったんでしょうか?
私、実は一度も「デザイナーになろう」と思ったことがないんです(笑)。「ファッションデザイナー」という響きが自分の活動的にもあまりしっくりきていないので、そう言ってしまっていいのか未だによくわからなくて。私の中では、服を作ることだけが目的ではなく、“コミュニケーションの道具の一つ”として服があると考えています。例えば、服を作っているからみんなが展示会という空間に来てくれるといったような、その存在を介して人と交流できる道具のようなものとして見ているので、私の中で「服」はお茶や食べ物と一緒なんです。
ー「デザイナーになろうと思ったことはない」というのは驚きです。
もしかしたら、私は“パリコレ”のようなものを目指していないから、こういうスタイルになったのかもしれません。上京してバンタンデザイン研究所に入った時に初めて海外のコレクションに触れたのですが、当時は正直「異世界だな」と思ってしまって。服や装いは好きだし楽しいという気持ちはあるけれど、所謂“ファッション”には殺伐として戦っているようなイメージがずっとありました。でも、私はあまり戦いたくないし、自分のものづくりのルーツとも合っていないように感じ、以前から違和感を抱いていたんです。もちろん、「服」という共通の土俵に立つ以上、同じ枠組みの中で戦うことは多少なりとも必要ですし、友達のブランドのショーを見に行くのも好きですが、自ら生み出すという部分に関しては、どうしても自分のルーツである「村」という部分を大事にしたいし、穏やかでいたいという気持ちがあります。

だから、今回新しくお店を作ったのもそうですが、自分の島を築いて、その中で共感してくれる人や興味を持ってくれる人に対して自分の思う“ファッション”や思想を提案し、何かをゆるやかに与えることができたらいいなと考えています。「布に触っていたい」「自分や誰かを可愛くできる道具を作りたい」「服を与える人になりたい」、そういう思いを総合して見た時に、行き着いた先が「デザイナー」という枠組みの中に入っていたんだと思います。
ーでは、苅田さんが実際にブランドを立ち上げるまでは、どのような道のりだったのでしょうか?
高校時代は、実業高校の生活文化科というところで「衣文化」を中心に学んでいました。全員が衣服と食物の検定を取らないと卒業できない学科で、みんなでハーフパンツやシャツを縫ったり、文化服装学園式の教科書で学びながら自分でパターンを引いてジャケットを縫ったり、コンテストに応募する作品や卒業制作を作ったりと、そこで一通りの縫い方は教わりました。そんな中で、被服の先生に「りっちゃんは服の道に進んだ方がいいよ」と勧めてもらって。最初は文化服装学院を目指していたのですが、学費のことなどもあり、最終的には母親が見つけてくれた1年から通えるバンタンに入学しました。
でも実は、当時はお店を開いて作りながら接客するようなことをやりたいと思っていたので、体験入学したのも、実際に入学が決まっていたのも「ビジネス科」だったんです。それなのに、入学式の日にいきなり「やっぱり変えていいですか?」と相談して、服を作るコースに急遽変更して飛び入り参加することになって(笑)。
ー入学式で「何か違う」と感じたということでしょうか?
自分ではずっとビジネス科でいいと思っていたんですが、たまたま入学式に向かう途中の電車で、当時東京で通っていた古着屋さんの店主にばったり会ったんです。「これから入学式なんです」と話をしていたら、「ビジネスはどこの学科に行ってもついてくるものだから、絶対作る学科の方がいいよ」と言われて。それで、不安になって学校に相談したら柔軟に対応してくれ、急遽変更してものづくりの学科に入ることになりました。そこで偶然会っていなかったら人生が変わっていたかもしれないと思うと、すごく感謝していますね。
バンタンの衝撃的な授業で見出した“ワールド全開”の自分らしさ
ーバンタンでは、どんなことを学びましたか?
当時のバンタンは、アントワープ王立芸術アカデミーの思想や授業方法を採用していて、1年間に第1〜4までの4つのタームがあったのですが、それぞれがすごく衝撃的な内容の授業で。例えば第1タームでは、最初の授業でいきなり「生成り色のシーチングのみを使って自分の思うスカートの形を作る」という課題が出されたのですが、スカートの縫い方を教わるのではなく、一度「縫う」という概念を取り払って、接着剤を使ったり、針金に布を纏わせたりしながら思い思いの形に落とし込むといった、“デザインはなんでもあり”という自由さを学ぶような内容でした。
続く第2タームでは、デザイン画を描かずに、まずは布と布の間にボーンになるようなものを挟んで立体的なテキスタイルを作り、それをボディに巻いてドレーピングでドレスを作ることを、第3タームでは、絵画を見て、当時の人々が着ていたであろう服の時代背景や構造、デザインなどを全て調べて、コルセットをはじめ、内側から全ての服を作るということを課題としてやりました。
ーオーソドックスな服作りの授業は1つもなかったんですね。
だから「普通の服作りを教えてくれ」と不満を言う学生もいたのですが、先生たちも「それなら他の学校に行ってよ。綺麗な服はいつでも作れるんだから」みたいな感じで(笑)。でも、そうやって半年以上たくさん遊んで試行錯誤して、自分は何が好きなのか、何がやりたいのかということも含めて新しい部分をどんどん開拓していったからこそ、技術を応用したり、自身のクリエイションを客観視したりできるようになったんです。おかげで、第4タームの終了展や2年目にいざ自分のコレクションを作る時には、純粋に楽しみながら創作することができました。
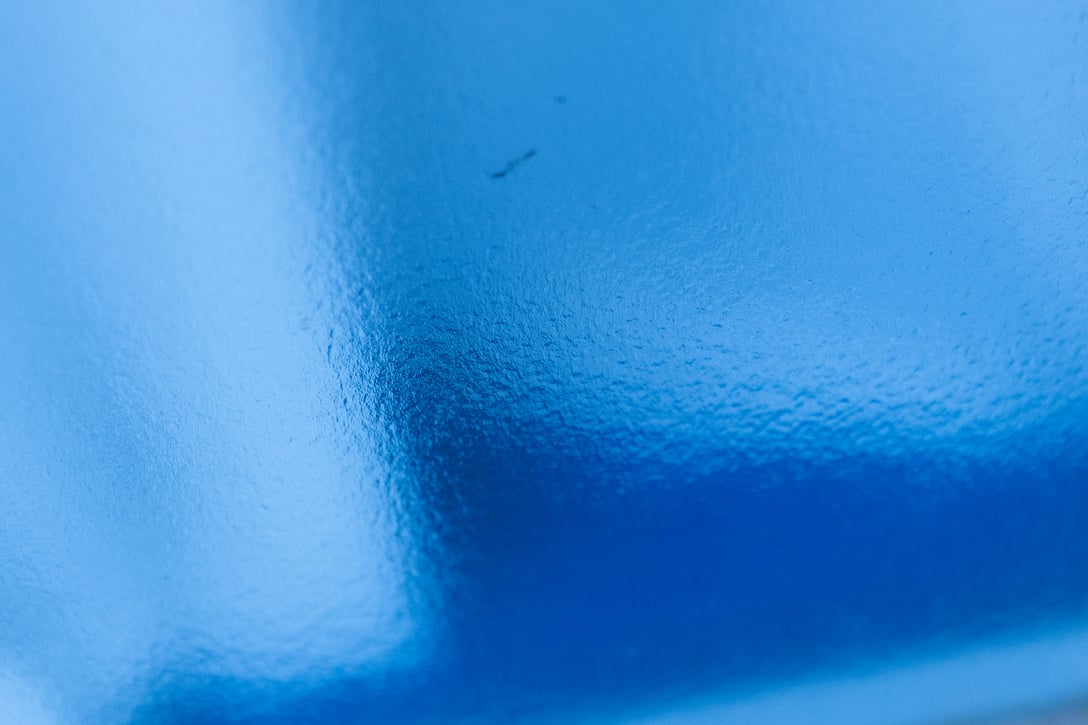
当時先生だった「エズミ(EZUMi)」のデザイナーの江角泰俊さんにも「もう苅田さんにアドバイスすることないから、自分のワールド全開で好きにやってね」と言っていただいたりもして。私は元々縫うことができたから、いきなりぶっ飛んだやり方でも臨機応変に対応できたというのもありますが、バンタンで学んだことは今に活きていますし、選んでよかったな、と心から思っています。
ーバンタンで、印象的だった人との出会いはありましたか?
とても大きな影響を受けた1つ上の女性の先輩がいました。その方は、ウィメンズ的な思想や要素を取り入れてアンニュイなメンズ服を作る人だったのですが、入学してすぐに、先輩のクリエイションを見てとても素敵だと感じて。それでよく休み時間に訪ねに行ったり、その方がコンテストでショーをやることになった時にコレクション製作のお手伝いをさせてもらったり、春休みには私がウィメンズ、先輩がメンズを担当して2人で「布団」をテーマにした合同展を開いたりもしました。周りにいた他の先輩たちも、在学中に「ミキオサカベ(MIKIOSAKABE)」のランウェイでモデルとして歩いた人や、「アキラナカ(AKIRANAKA)」に就職した人がいたりと、モードやコレクション寄りの思想の人が多かったので、そんな先輩たちの考えやものづくりに影響されて、“コレクション”として洋服を展開していくことや、デザイナーズブランドへの興味を持つようになりました。
ー「梨凛花〜rinrinka〜」は、授業でのコレクション製作がスタートだったのでしょうか。
そうなのですが、授業の時はまだ「梨凛花」という名前は付けていなくて。その時は、先輩との合同展で作った「布団」というテーマから派生した、真っ白なコレクションを制作しました。日本の昔の布団の内側の端っこに付いているようなリボンや、ちょっと野暮ったい花柄などをディテールとして取り入れた、パンツやキルティングのキャミソール、フード付きのドレスなどから成る3体のコレクションだったのですが、初めて自分で納得のいくものができて。自分の家のロフトで女の子のモデルに着てもらって作品撮りもしましたね。

実際に「梨凛花」としてやり始めたのは、在学中に渋谷PARCOでバンタンの在学生と卒業生のポップアップをやる機会があった際に、自ら手を挙げて参加したことがきっかけでした。その時に「自分は何がやりたいんだろう」と考えてみたら、私は幼少期から和裁士だった母の影響を強く受けてきたので「和テイストの上品な凛とした女性像」がずっと好きだったし、「布団」というモチーフにも日本的なところがあるなと気づいて。それで、布団の衣装にスタイリングできるような、絞りのような細工をしたお花モチーフの髪飾りやリュック、押し花をビニールでサンドした巾着バッグといった、古典的で日本らしいデザインを取り入れた小物を作りました。
そして、先生から「イベントに向けてブランド名も考えておいてね」と言われ、自分の名前の字である「梨」と、「凛」とした女性像のイメージだった「梨の花」を組み合わせた、「梨凛花」という名前を付けたんです。だから、「ブランドを立ち上げた」というよりも「イベントに間に合わせなきゃ」という感じで急遽ブランド名を付けたのが始まりでした。
ーそのようなスタートだったんですね。「梨凛花」としての初のポップアップはいかがでしたか?
最初、先生には「こんなの売れないよ」と言われていたのですが、当時私はツイッターで2000人くらいフォロワーがいて、インスタグラムもちょうど始まった頃だったのでSNSにイベントのことを載せたら、それを見てくれた方たちが買いに来てくれて、作ったものが完売しちゃったんです。しかも、その頃インターンとして働いていた「ジェニーファックス(Jennyfax)」のデザイナーのシュエ・ジェンファン(Shueh Jen-Fang)さんも見に来てくれた時に「いいじゃん」と褒めてくださって。それもあって、当時ジェニーファックスが卸していたセレクトショップ「マカロニック(MACARONIC)」に、梨凛花の小物も置いてもらえることになりました。自分がやりたかった“お店屋さん”の第1スタートという感じで、「楽しいな」という気持ちでやっていましたね。
3ヶ月泣きながら準備した、初めてのファッションショー
ーバンタン卒業後、「梨凛花」はどのように歩んできたのでしょうか。
実は卒業直後は、梨凛花としてブランドをやっていくのかどうかも微妙な状況でした。「とりあえず自分でやっていこう」と思い特に就活もしていなかったのですが、いざ卒業して、母からも一切お金は出さないと言われたら、東京で一人でやっていけるのかどうか急に不安になってしまって。それでつい弱気になって、サンリオピューロランドの着ぐるみの衣装を作る仕事の募集を見つけてやろうかと本気で悩んでいたのですが、当時東中野で一緒にルームシェアをしていた女友達が、「ピューロランドなんてまず寝坊して通えないから受けない方がいいし、りっちゃんはもうたくさんファンもいるんだから大丈夫。絶対に梨凛花でやっていくのがいいよ!」と怒ってくれて、厳しくも力強く背中を押してくれたんです。
ーその時も、また身近な人の言葉が後押しになったんですね。
「目標を決めた方がいいよ。まずは自分でギャラリーを借りて展示会をやったらどう?」という友達からのアドバイスを受けて、「じゃあ21歳になる誕生日までにやろう」と決めて実際にギャラリーを借り、パルコのポップアップに出品したような小物を中心に1回目の展示会を無事開催しました。その後は、誘ってもらったイベントなどに参加したりしながら、サーティーワンのアルバイトと掛け持ちで楽しくのほほんと制作していたのですが、転機になったのは、同じ年の冬に開催した2回目の展示会でした。その時も、私は中原淳一さんのイラストの女の子みたいな髪型になれる三つ編みのパーツが付いたヘアバンドや、茶道の服紗をモチーフにした赤いベルベットのバッグといった小物を作って展開していたのですが、展示会を見に来てくれたジェンファンさんが突然、「梨都子、ファッションショーに出てみない?」と言ってきたんです。

当時「ここのがっこう(coconogacco)」のメンバーだった、「ケイスケヨシダ(KEISUKEYOSHIDA)」「コトハヨコザワ(kotohayokozawa)」「ソウシオオツキ(SOSHIOTSUKI)」の3ブランドが、「東京ニューエイジ」という若手デザイナーを集めたプロジェクトのファッションショーに出ることになっていました。でも、「4人出なきゃいけないのに今3人しかいないから、梨都子出てよ」と。ショーは2015年3月に開催予定で、その時はすでに2014年の12月末。他の3人は1年かけて制作したコレクションがほぼ完成しているのに、私は小物しかなくてまだ服はないという状況だったのですが、ショーに出るかどうかという大きな決断を、たった5日で決めなくてはいけなくて。
ーそれはなかなか難しい選択ですね。
結局頑張って出ることにしたのですが、それからの2〜3ヶ月は今思い出してもしんどくなるくらい、人生で一番忙しい、泣きながら服を作る日々を過ごしました。ルックの一部には、卒業制作として作った「1980年代風のお母さん」をアイドルに見立てて、若い頃の母の顔写真をプリントしてリボンを100個くらい付けた、ちょっと狂ったデザインのキャミソールをインナーとして使ったりもしていました。当時の私は「公の場に出るなら完璧な状態で出したい」とかなりストイックで、それ以外はほとんど全て一からデザインして。ブラウスからパンツ、ブルゾン、スカート、ワンピース、バッグ、髪飾りまで、5体分のルックを新たに作ったので、本当に遊ぶ時間も休む時間もなく、昼の12時から朝の7時までずっと制作して、寝て、また起きて朝まで制作するという生活を約2ヶ月続けました。

「東京ニューエイジ」の2015-16年秋冬コレクション
Image by: FASHIONSNAP

「東京ニューエイジ」の2015-16年秋冬コレクション
Image by: FASHIONSNAP

「東京ニューエイジ」の2015-16年秋冬コレクション
Image by: FASHIONSNAP
実はショーがあった3月には、デザイナーの山縣良和さん、坂部三樹郎さんがプロデュースした、渋谷PARCOでの「絶・絶命展〜ファッションとの遭遇」も含め、合計6つのイベントに出ることになっていて。だからお金もないしとにかく忙しい、怒涛の日々でしたね。
ーよくそれを全部引き受けてやり遂げましたね。
今はもう少し緩くやっていますが、「頼まれたものは全部やる」というのが当時の私の考えで。でもショーへの参加を引き受けたことが、自分にとって大きな分岐点になりました。色々なメディアに「梨凛花、デビュー」と載ってしまったので、もう服のブランドとしてやらざるを得なくなったんです(笑)。それから、日本テレビの「しゃべくり007」に出演したきゃりーぱみゅぱみゅさんが衣装として着てくれたり、「装苑」で元欅坂46の平手友梨奈さんがアクセサリーを付けてくれたり、台湾のアーティスト Yoga LinさんのMVで小松菜奈さんが着用してくれたりと、自分が好きだった方たちに梨凛花の服を着てもらうという夢が、わけもわからないうちに気づけばどんどん叶っていきました。
ーお話を伺っていると、“目指した”というよりも、様々な偶然や出会いがきっかけになって人生が動いている、という印象を受けました。
確かに、偶然が重なったり、いろいろなご縁があった時に私自身が「チャンスだ」と思ってしがみついたことが別の何かに繋がったりと、そういう巡り合わせが多かったですね。

2016−17年秋冬コレクション
Image by: 梨凛花〜rinrinka〜

2018年春夏コレクション
Image by: 梨凛花〜rinrinka〜
趣味の延長をビジネスにする術を教えてくれた「デザビレ」
ーその後、FASHIONSNAPもオフィスを構えていた「台東デザイナーズビレッジ(以下、デザビレ)」に入居。
当時は、ブランドをビジネス的にどうやっていったらいいのか全くわからなかったんです。そんな時に知ったのが、「ミキオサカベ」でのインターン時代から繋がりのあった「アキコアオキ(AKIKOAOKI)」の青木明子さんが入っていた、デザビレの存在でした。デザビレはクリエイターのビジネス成長を支援してくれる施設ですが、そこに入ったことで、それまではアルバイトをしながら趣味の延長のようにやっていたものを、「ビジネス」として1本でやっていく具体的な方法を教えてもらいました。
ーデザビレに入る前は、どのようにやっていたんですか?
23歳の頃までは、平日は朝から夕方まで制作をして、夕方から夜までは家賃を稼ぐためにサーティーワンで週5日アルバイトをするという、ずっと服作りとバイトに追われて遊びに行く時間もないような生活を送っていましたね。当時は生産や量産の方法もわからなかったので、新作のデザインも、型紙も、縫製も、オーダーが付いた分の服や一点物の制作も全て自分でやっていて。でも、このままずっとこれを続けて生きていくことはできないし、これからどうしていったらいいのかと真剣に悩んでいました。

デザビレに入ってまず言われたのは、普通はファン作りができる前に量産して在庫を抱えてしまい、どうしたら服を買ってもらえるかを考えていくブランドが多い中で、「もう苅田さんはファン作りができているから、ビジネス的な仕組みを変えれば絶対大丈夫。今まで一人でよく頑張ったね」ということでした。その言葉を聞いた時は、泣きそうになりましたね。デザビレでは、ビジネス的なアドバイスをしてくださる「村長」に、半年に1回、売上目標とその達成状況や、使った経費の内訳、展開先の計画などを全てまとめた資料を作って、事業報告のようなことを必ずしなければいけないのですが、ブランドの現状や今後に関して客観的なアドバイスをしてもらえるのは、本当に為になりました。
ーデザビレで学んだ一番大きなことは?
「自分の手で縫うことに執着しなくていい」と気づけたことですね。デザビレに入った1年目の後半くらいの頃に、結構手の込んだデザインの服に1型で20オーダーついた時、「これを全部縫いながら新作を作るのは無理だ」と初めて心が折れたんです。それまでは、誰かに頼ることは苦手だし甘えだと思っていたのですが、その時は村長からも「これは誰かに頼まないと絶対無理だと思う。苅田さんは誰かに頼んだり頼ったりすることを身に着けた方がいいよ」とアドバイスをもらって。それで、バンタン時代の先生に相談して紹介してもらった生産工場さんに、ビクビクしながら自分で引いたへなちょこパターンを持って行ってサンプルを作ってもらったら、ものすごく綺麗に仕上げてくださって。“プロ”の仕事に感動したんです。その時に、これまでは「手作り」であることを魅力や強みとしてこだわってやってきたけど、「少し頼ってみてもいいのかもしれない」と初めて自分の中で許すことができました。

それから段階的に、量産やサンプル製作を少しずつ工場さんにお願いしていって、梨凛花の最後のコレクションからは、サンプルの生産も全て依頼するようになりました。初めは金融機関から借り入れをすることや、外部に頼むことでお金が掛かることへの怖さもあったのですが、村長からも「オーダーが付いてるなら、それは必要経費だから大丈夫。お金を回して行かないと売上にも繋がらないから」と言われて。それで色々と踏ん切りがついて、デザビレにいる間に、製作や生産方法、資金面での切り替えをすることができました。
ーデザビレで得たものは大きかったんですね。
かなり大きかったですね。「自分で縫う」ということを手放せたからこそ、余った時間でSNSを更新したり、写真を撮ってお客さまに伝えたり、色々なものを見に行ってインプットしたりと、今までできていなかったところに時間をかけられるようになりました。その中で、自分がこれから一番やっていきたいのは、「縫う」ことではなくデザイナーとして「表現する」ことだと思えるようにもなったので。

2018-19年秋冬コレクション
Image by: 梨凛花〜rinrinka〜

2019-20年秋冬コレクション
Image by: 梨凛花〜rinrinka〜
「梨凛花」から「RITSUKO KARITA」へ
ー2020年春夏を最後に「梨凛花」を休止し、現在の「RITSUKO KARITA」をスタート。どういった意図があったんですか?
20歳前後の頃に梨凛花を始めてから6年間続けて、自分自身も年齢を重ねていく中で、次第に見るものや感じるものに、いい意味で“移ろい”があったことが一番の理由ですね。元々梨凛花は、毎回物語性の強いコンセプトを明確に決めていたので、その世界観を表現するためにデザインも華美で衣装寄りなものが多かったし、お客さまの中でもそのイメージが確立されていました。でも、自分が次第に建築や美術などを好きになっていった時に、ブランドとしてもアイテムやスタイリングとしても、もっと「余白」を作れないかなと考えたんです。

2020年春夏コレクション
Image by: 梨凛花〜rinrinka〜

2020年春夏コレクション
Image by: 梨凛花〜rinrinka〜
台湾を訪れた時の記憶から作った最後のコレクションでは、自分の中で結構やり切った気持ちもありましたし、2020年はちょうどデザビレを出て、アトリエと住まいを東京・鶴川の一軒家に移動するタイミングでもありました。だから、場所の移動とともに、ブランド名やコンセプト、在り方も含め、今自分の心にあることを全部変えたいし、変えてもいい時なのかなと。それで、引き続き華美な衣装寄りのものを提案する「リッチ(rich)」や、余白があって日常で着やすいようなアイテムを提案する「プレーン(plain)」などいくつかライン分けをして、梨凛花を踏襲しつつも、より生活に寄り添ったTPOによって選ぶことができるブランドにしようと、自分の名前を掲げた「リツコ カリタ(RITSUKO KARITA)」として新たに始動することにしました。

2020-21年秋冬コレクション「plain」ライン
Image by: RITSUKO KARITA

2020-21年秋冬コレクション「rich」ライン
Image by: RITSUKO KARITA
ー「リツコ カリタ」では、コレクションを作る際に何を着想源にされているのでしょうか。
ブランド名を自分の名前にしたこととも繋がるのですが、コレクションのテーマとしては、私自身が日常の中で出会った人や作品、景色、五感や第六感で感じたものなどをキーワードにしながらデザインに取り入れています。映画や本、写真集などで見た色合いや空間だったり、「匂い」からインスピレーションを得て作ることもありますね。毎シーズンのテーマには、自分自身がこの半年で感じたことが全て反映されているので、ブランドとしての軸はありつつも、今後どうなっていくのか自分でもわからないところも、結構楽しいなと思っています。
ーこれまでに影響を受けた、具体的なものや作品は?
例えば、日本画家の小倉遊亀さんの絵画の色使いや、日常と創作が繋がった、暮らしながらアウトプットするような仕事のスタイルであったり、スウェーデンを代表するデザイナー兼陶芸家のインゲヤード・ローマン(Ingegerd Raman)さんの展示や作品から学んだ「余白」や「引き算」の美しさや考え方、フランスの作家 フランソワーズ・サガン(Françoise Sagan)のぶっ飛びつつも人間味や愛に溢れた生き方や精神性、映画「汚れた血」(監督:レオス・カラックス/1988年)や「山の焚き火」(監督:フレディ・ムーラー/1986年)などの作品がもつ狂気や不気味さ、高野文子さんの漫画作品「るきさん」に描かれる平凡な日常の中のユーモアであったりと、すごく色々なものから影響を受けています。

直近の2024年春夏コレクションでは、生活の中でコップに注いで飲んだ西瓜ジュースの赤からはじまって、19歳の頃に読んだ江國香織さんの小説「すいかの匂い」に漂う夏のひんやりとした気配や不気味さ、その不気味さから連想した画家の五木田智央さんの作品、と繋がっていったものを、赤という色や西瓜の種をイメージしたドット柄、写真のコラージュといった様々な要素に落とし込んで表現しました。

ーサガンの生き方や精神性などにあるような“狂気”といった要素は、ブランドのイメージからすると少し意外でした。
自分ではそこまで狂ったことや激しいことはできないかもしれないけれど、私が力や思いを炸裂させる場である「ものづくり」をする時の精神的な部分では、サガンくらいやりたいことを全うできたら、生き方として格好いいなと思っていて。私自身が彼女に憧れのような気持ちを抱いたり影響を受けたりしているように、1人の女性としての私の生き方や作る服が、誰かの心に印象的なものとして残ったらいいなというのは、一つの目標かもしれません。
ー実際の服作りやデザインとしては、どんなところを大切にしていますか。
もちろん「服」として形にはしなければいけないのですが、自分としては結構「曖昧なもの」が好きなので、テーマやモチーフとしてあるものをデザインに落とし込む時は、あえてぼかして撮った写真を使ったり、一部分に断片的に取り入れたりといったことを意識的にやっています。同じように、素材もシアーなものを用いたりそれをレイヤードすることで、空気を纏っている感じや、肌が見えてもいるし隠れてもいるような曖昧なフィルターがかかっている様を可視化することを目指している部分もありますね。

2023年秋冬コレクション
Image by: RITSUKO KARITA

2024年春夏コレクション
Image by: RITSUKO KARITA
そして、「日常の中で着やすい」という部分を大切にしているので、アイテム自体をアバンギャルドにするのではなく、スタンダードなアイテムの中に非現実的な要素をどうデザインとして落とし込むか、ということをいつも考えています。例えば今シーズン作ったデニムスラックスも、形はスタンダードだけど、ボディの前面は黒なのに背面は水色になっていたり、一部分だけ透けていたりと、五木田智央さんの絵から着想を得たコラージュの要素を取り入れていて。人が日常の中で時々映画を見に行って非現実的な時間を味わうように、仕事にも着ていける服だけど一部分に非現実的な要素が入っていたり、コーディネートによってはお出かけや旅行はもちろん晴れの場にも着ていけるような、日常と非日常両方に寄り添う服にできたらと思っています。


ー苅田さんは洋服のデザイナーに限らず、映画や美術、食にまつわるコラムの執筆や母校バンタンでの講師など、仕事は多岐にわたります。ご自身の働き方や在り方について、どのように考えていますか?
私は、たまたま自分にとって一番身近で表現のしやすい手段が「ファッション」や「服」であり、それが得意だったから「ファッションデザイナー」という職にうまく就けたのではないかと思っています。一方で、寝る、ご飯を食べる、お茶を淹れるといった生活の中の行動や所作の一部として「服作り」があると捉えているので、どれか一つに定めるのではなく、空間や香りなども含めてトータルで提案することを一番やりたくて。だから、ただ服をデザインしているだけでは、自分のやりたいことが100%できているとは言えないんです。香水のような「香り」も纏うことができるという意味ではファッションでもあり生活の一部でもありますし、コラムなどでの言葉を通して、私自身の人となりや思想などを表現したり補ったりできる部分もあるので、色々な角度からの表現方法があるからこそ、自分が今やりたいことを見せられているのではないかと考えています。

ー過去にはかなり無理をして働いていた時代もあった中で、今の苅田さんは「働くことと暮らすことのバランス」について、どんなことを大切にしていますか?
昔必死にやっていた時代があるからこそ今があるとも思っていますが、最近は20代前半の頃とはまた違った空気感で生きていますね。もちろん繁忙期などで頑張らなければいけない時はありつつも、やっぱり自分が心地いい状態じゃないといい服も作れない。だから、今はなるべく仕事の途中でお茶を飲んでリラックスする時間を設けたり、仕事の帰りに映画を見たり、料理も好きなので帰ったら夕飯を作ったり、自分が気になっている人たちに会いに行ったりと、そういったデザイン以外の時間も同じくらい大切にしながら、ちゃんと呼吸ができるような生活を心掛けています。先程着想源の話でも触れたように、デザインは自分が見たものや感じたものから出てくるので、今は生活と仕事の境をあまり作りすぎずに、今の気持ちや状態と対話して確認しながら、素直な自分でいることを意識して仕事も生活もしているかもしれません。
新店舗は「私たちのものでもありみんなのものでもある」場所
ー鶴川のアトリエを出て、今回四谷三丁目に新たに事務所兼店舗「S(︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎)」をオープンした理由を教えてください。
以前の鶴川のアトリエ兼住居は、建物の広さや、都心からの小旅行的な距離感と環境もとても良くて気に入っていました。でも、お客さまが忙しい日々を過ごす中で、貴重な時間を使って展示会などを見に来てくださっていることを考えると、より都会的な場所に構えた方が良いのではないかと思ったことが一番の大きな理由です。都会的な立地で立ち寄りやすいけれど、少し現実から離れてゆったりした時間を過ごせるような、ひっそりとした場所がいいなと思って探した時に、色々な条件が揃ったのがこの物件でした。

ー新事務所兼店舗は、内装・インテリアデザイナーの佐藤裕樹さんと共に運営されていると伺いました。
1年ほど前に、ハンガーラックを作ってもらおうと思って佐藤くんと初めてお会いしたところ、いきなり「一緒にお店をやりませんか」と声をかけてくださって。当時、私はアトリエと住居が一緒になっていたので、常にお客さまに来ていただけるようなスペースにはなっていなかったんです。一方佐藤くんも、自分が手掛けた什器を展示する場所は欲しいけど、誰もいないショールームにただ置くのではなく、実際に使ってくれる人がいて、見てもらえる場所に置かないと意味がないと考えていたようで、双方の利益が一致したので一緒にやることになりました。
ー店内の設計や什器は、全て佐藤さんが手掛けているのでしょうか。
設計からインテリアのデザインやアイデアまで、基本的にすべて彼が手掛けています。例えば、この木とアクリルでできた大きなテーブルも、作業台はもちろん、様々な展示方法に応じた什器として使用できるように高さを変えられる仕様になっていて。カーテンの位置も、向こう側に奥行きを持たせることで、在庫や見せたくないものを収納できるストックスペースを作ったり、全身鏡を置く代わりに入口のドアの内側を全面鏡張りにしたり、あえてコンセントにカバーを付けずに中の青いパーツを見せたままにしたりと、建築や空間デザインの視点や知識があるからこそのアイデアやデザインをたくさん反映してもらいました。私自身もデザインの面でものすごく刺激を受けています。

佐藤裕樹がデザインを手掛けた、高さを変えられるオリジナルのテーブル
そのほか、椅子は私のアトリエで以前使っていたものも含め、あえてデザイナーズのものをバラバラに並べたり、自分たちの手で拾ってきた石を入口に置いたりと、自分たちのルーツにまつわるものも取り入れています。


ー新しいお店では、どんなことをしたいと考えていますか?
ベースはアポイント制のお店なのですが、まずは通常営業のスタイルとして、少しユニークな入店方法を2種類設けたいと思っていて。1つは、入場料を1000円いただく代わりに、お茶やお菓子などを色々提供させていただくというもの。もう1つは、まるで友達の家に遊びに行くみたいに、入場料の代わりとして何かお菓子を持参してもらうというものです。お菓子を持ってきていただいたら、インスタグラムのストーリーズなどで「本日いただいたお裾分けです」と投稿してご紹介しつつ、それをみんなで食べたりお茶を楽しんだりして一息つきながら、たまたま居合わせた人と話したり、服を試着したり、お茶や服を購入したりと、とにかくこの場所でゆっくり過ごしてもらえたらと考えています。
ー入店方法の時点でかなりユニークですね。
「ただ服を買いに来て帰る」という場所にはしたくなくて。来店される方には30分でも1時間でもいいからゆっくり滞在してもらって、まずは座ってほっと一息ついて休んでもらいたいという思いがあるので、そのような仕組みを選びました。また、リツコ カリタ以外のブランドも定期的にお招きしてポップアップイベントなどを開催することで、これまでウィメンズメインのリツコ カリタだけでは足を運んでいただけなかった、老若男女もっと幅広いお客さまに来ていただいたり、双方のお客さまにとっての人や物との新たな出会いや交流の場になるようなことができたらと考えています。

ーなぜ、そういうことをやりたいと思ったのでしょうか?
これまでの展示会やお茶会などでの経験から、お客さまが抱く、展示会に対する敷居の高さや試着のしづらさなどをもっと払拭できたらという思いが強くなったからです。みなさん、最初は行きづらい、試着しづらいという気持ちがあるようなのですが、一度来てもらったり、座ってお茶を飲んだりすると、色々なことを話したり、気軽に試着したり、2回目以降も来店してくださるようになったりするんですよね。私自身も境界線がない方が交流がしやすいタイプなので、ここは私のお店というよりも、「私たちのものでもありみんなのものでもある」をテーマにした場所にしたくて。もしかしたら私たちもここで仕事をしているかもしれないですが、来る人も買ってきた本をここで読んでもいいし、自分の家みたいにくつろいでもいいし、物も買えるといったような、衣食住の延長のような形で、この場所で服も見てもらえたらいいなと思っています。
ー今後、苅田さんがやっていきたいことを教えてください。
私の夢が「お店を持つこと」だったので、まずはそれがやっと実現したからこそ、この場所をどう面白くしていけるかということをやっていきたいと考えています。通常営業だけではつまらないので、例えば映画からインスピレーションを受けたコレクションなら、映画を上映して世界観をより味わってもらいながら服が買えるようなイベントを開いたり、洋服のお直しのワークショップを開いたり、ヘアアクセサリーのブランドとコラボして作ったアイテムを買ってくれた方に、美容師さんがそれを使ったヘアアレンジを施して写真撮影ができるようなイベントを開催したりと、様々な方やブランドとの交流を交えた企画をやってみたいです。

ー既に素敵なアイデアが色々膨らんでいるんですね。
それ以外にも、男女関係なく着ていただけるようなユニセックスで着られるサイズやデザインのアイテムを作ることや、カーテンをはじめとしたインテリア関連の布物アイテムも作ってみたいなと考えています。
ー最後に「ファッション」について、苅田さんが希望と違和感を感じている点をそれぞれ教えてください。
服は一度形にするとずっと残ってしまうものなので、いかに環境負荷に加担しないようにできるかという部分と、一方で自分は服を作って売らなければブランドとして生存ができないという部分もあり、その矛盾にどう折り合いをつけていくべきなのか、本当にこの仕事を続けていくことが一番いいのかといった葛藤は常に心にあります。
それと同時に、私自身も含め、服は人が生活する上での喜びや楽しみ、救いにもなりうるものだと思っているので、その服を着ることで「この先も頑張ろう」と思えるような、お客さまにとって救いになるようなものを作っていけたら嬉しいですし、それが自分にとっての希望でもあると感じています。どの目線で見て、どのように活動すべきかという答えはそう簡単には見つからないですが、先程お話しした「お直し」の活動や、在庫が残ったアイテムに装飾を施してアップサイクルして販売することなど、まずは自分にできるところからやっていけたらと思っています。

text & edit:Erika Sasaki(FASHIONSNAP)
photographer:Yuzuka Ota(FASHIONSNAP)
■「S(︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎)」
所在地:東京都新宿区舟町10-17 ビレッジ四ツ谷3ビル2F 202号室
公式インスタグラム(※フォローは承認制)
■リツコ カリタ:公式オンラインストア/公式インスタグラム
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【インタビュー・対談】の過去記事
RELATED ARTICLE
関連記事
READ ALSO
あわせて読みたい
RANKING TOP 10
アクセスランキング

銀行やメディアとのもたれ合いが元凶? 鹿児島「山形屋」再生計画が苦境





























