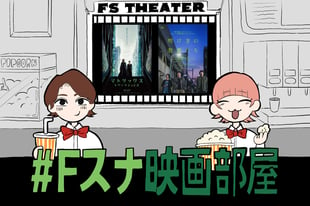スウェットは映画「逆光」のオリジナルグッズ。イラストはイラストレーター たなかみさきがデザイン
Image by: FASHIONSNAP
12月18日に渋谷・ユーロスペースで公開を迎えたインディーズ映画「逆光」が今、20代の若者を中心に話題を集めている。監督を務めたのは今回が初監督作となった俳優 須藤蓮。地方から配給・宣伝活動を行うなど、映画業界の長年の慣習に抗った新たな試みは、彼らと同世代の若いクリエイターを巻き込みながら大きなムーブメントを生み出しつつある。朝ドラへの出演など役者としてのキャリアを着実に積む中、俳優業をセーブしてまで映画制作に心血を注ぐ須藤蓮とは、一体何者なのか?25歳の若き表現者の飽くなきクリエイティブに対する探求心、周囲を巻き込む行動力の源に迫った。
映画「逆光」
同作で主演・初監督を務めた須藤蓮と、「ワンダーウォール」「ジョゼと虎と魚たち」「カーネーション」などの作品で知られる脚本家 渡辺あやが企画・制作した自主映画作品。舞台は1970年代の真夏の尾道。主人公 晃は好意を寄せる大学の先輩 吉岡を連れて帰郷。幼馴染の文江やみーこの4人で交流する中で、みーこへの眼差しを熱くしていく吉岡の姿に晃は苦悩していく。須藤のほか、中崎敏、富山えり子、木越明らが出演。国際映画祭「台北金馬映画祭」に正式出品した。映画の舞台となった尾道から上映、配給、宣伝活動をスタートさせるなど、映画業界の常識を覆す取り組みが注目を集める。2022年1月7日にはアップリンク吉祥寺で公開予定。
ADVERTISING
須藤蓮
俳優・映画監督。1996年東京都出身で、慶應義塾大学法学部に在学中。スターダストプロモーションに所属し、2017年から俳優としてのキャリアをスタート。これまでに「ワンダーウォール」「なつぞら」「いだてん〜東京オリムピック噺〜」などの話題作に出演。2022年1月クールの吉田鋼太郎主演フジテレビ系連続ドラマ「おいハンサム!!」では漫画家 ユウジ役としての出演が決定している。
クラスの落ちこぼれから慶應進学、そして俳優へ
ー現在、慶應義塾大学法学部に在学中ですが、元々司法界に興味があったんですか?
高校生の頃、全く勉強ができなかったんです。下から数えた方が早いくらい成績が悪かったんですが、大学受験の時に一念発起して。猛烈に勉強して慶應に入ったんです。でも、法学部は就職に強いからという理由だけ選んだので、法律が勉強したい気持ちは全然無かったんですよね。
ー入学後はどのような学生生活を?
勉強ができないという強いコンプレックスは慶應に受かったという成功体験によって解消されましたが、一方で変なスイッチが入ってしまって。テスト中毒というのか、競争して良い結果が出れば人から褒めてもらえる。それだけのために頑張っていた時期がありました。それで司法試験の勉強に没頭するようになったんです。
ー大学2年生の頃には、司法試験予備試験の1次試験を突破したそうですね。
でも2次試験はボロボロの結果で。人から評価されるためにテスト勉強をして頑張ることに、燃え尽きてしまいました。その頃から徐々に、勉強さえ出来れば良い結果が出るといったことが通用しない世界への興味が湧き始めていました。それが結果として表現の道ということだったんです。
ー大きな挫折が表現の道に進むきっかけになった。
そうですね。あとは、同じ時期にもう一つ大きな出来事があって。東大に進学した友人が、新興宗教にハマって突然学校に行かなくなったんですよ。その友人が「勉強なんかしても、その先にはなにもない」と言い出し、口ではバカにしつつも心の中では真に受けてしまった自分がいて。彼の一件もあって「生きる意味とは?」とか「幸せってなんだろう」と真面目に考え出し、表現する道に行きたいという気持ちが強くなっていきました。よくよく聞いたら彼は、瞑想を行う合宿に行っていただけで、新興宗教にハマっていた訳ではなかったんですが。

ーなぜ表現の道を選んだのでしょうか。
自分の人生を振り返ってみると、自分の好きなことにチャレンジするといったことをずっとやってこなかった事に気付いたんですよね。子どものころから親に言われた習い事に中学受験、大学受験をして、大学に入ったら今度は褒めてもらえそうだからという理由で予備試験を受けるという。自分を表現するということを今までの人生でやってこなかったと改めて感じ、挑戦したい思いが次第に強くなっていきました。
ー現在は大学を休学中?
休学中です。今はやりたいことがはっきりとしているので、4年生ではありますが正直通い続けるべきか悩んでいます。
俳優業をセーブして映画監督の道へ
ー映画制作には元々興味があったんですか?
実は俳優を始める少し前から、映画「逆光」で撮影を担当したカメラマンの須藤しぐまさんと2人でずっと自主映画を撮っていて。僕は俳優として参加して、短編を7〜8作品くらい作りました。脚本がしょぼすぎて本当につまらないんですけど(笑)。
ー俳優としてのオファーが増えてきている今、なぜ映画監督に?
僕が憧れを感じる人って不思議と作り手の方が多くて。ドラマ「ワンダーウォール」(※)で出会った脚本家の渡辺あやさん(以下、あやさん)であったり、映画「よこがお」でご一緒した深田晃司監督であったり。その影響が多分にあると思います。映画を沢山見てきたわけでも無ければ、専門的な勉強をしてきたわけでもないので、自分では到底出来るわけないだろうと、心のどこかでぼんやりと諦めていたところはあったんですが、ゼロから皆んなで新しいことを立ち上げることにはとても興味があったんです。
※「ワンダーウォール」
京都発の地域ドラマとして2018年7月にNHK BSプレミアムで放送。京都の歴史ある学生寮「近衛寮」の建て替えを巡る、大学側と寮に住む学生たちとの対立が描かれる。脚本は渡辺あやが担当。須藤蓮、岡山天音、三村和敬、中崎敏、若葉竜也、成海璃子らが出演。2020年4月には「ワンダーウォール 劇場版」が公開された。
ー役者の方が参加するのは進行スケジュールが全て決まってからなので、初めから一緒に関わることは中々無いですよね。
そうなんです。役者って後から作品のチームに入るのに、最終的に役者が一番目立つことに違和感があったんですよね。自分が参加する頃には、スケジュールが組まれて、キャスティングや衣装、演出もほぼ全て決まっている状態。もちろん、芝居はとてもやりがいがあることなんですが、「一緒に衣装決めたかったな」とか「みんなでロケーション決めるのに必死になって歩き回りたい」と、どうしても思ってしまうんです。
ー参加する作品にはより深く関わりたいんですね。
自分がチームの中心にいないと落ち着かないんですよね(笑)。目立ちたいということとも違っていて、なんかしっくり来ないというか。人生で一度もリーダーシップを発揮したことが無いくせに、「ワンダーウォール」のヴィジュアルの並びで自分が真ん中にいた時にすごいホッとしたんです。
ーチームの中心にいるというのは、役者として主演を務めることとは必ずしもイコールではない?
そうですね、それは少し違う気がします。作品において、全体の動きを常に把握できる状態が落ち着くんだと思います。自分が中心となって主導権を握れる立場って何だろうと考える中で、映画制作の素晴らしさに気付いて。あやさんの薦めで映画を見だしてから、映画ってこんな面白くてこんなに可能性が詰まっているんだと知り、そこから一気に映画の世界に熱狂していきました。
ー映画制作は独学ですか?
独学です。それまでは映画をほとんど見たことがなくて、お恥ずかしい話なんですけど、昔は「テッド」と「ハリーポッター」ぐらいしか知らなかったくらい(笑)。色々な作品に触れる中で自分が撮りたいもの、見せたいものを突き詰めていきました。

ー映画「逆光」の撮影期間中は俳優業はセーブされていたんですか?
はい。撮影中とその前後の期間は「逆光」以外での芝居はやめていました。
ー所属事務所は理解を示してくれた?
割とすんなり理解を示してくれたと思います。それよりも、自分の心の葛藤を乗り越えるのが大変でした。「事務所の人にこんなこと言い出して良いのか?怒られるんじゃないか?」みたいな勝手な思い込みから来る恐怖心を抱いて、言い出せずに躊躇っていた時期は少しありました。
人気脚本家 渡辺あやとの出会い
ー映画「逆光」の脚本を手掛けた渡辺あやさんとは何年ぐらいの付き合いになりますか?
「ワンダーウォール」の作品で出会ったのが2017年だから4年くらいですね。結構長いです。
ー渡辺さんは須藤監督にとってどういった存在ですか?
作り手としての理想像。あやさん自身も彼女が作る文章も、ありのままの自然体の美しさが感じられるんです。人間としてもクリエイターとしても色々な場面で救われていますし、尊敬しています。僕があやさんから学んで吸収してきたことは、独り占めせずに同世代の表現に関わる多くの人にどんどん還元していきたいなと、出会ったときからずっと思っています。
ークリエイターとしては大先輩ですが、「逆光」チームでは同じ目標に向かって進む同志でもありますね。
業界でのキャリアの長さは全然違うので、学ぶ機会は本当に多いです。映画制作においては、監督と脚本家という対等な立場で向き合うことを意識しました。性別も違うし、年もすごく離れているので傍からみると不思議な関係性ですよね(笑)。でも、逆にそれが良かったと思うんです。誰でも輪の中に入ってきやすい場所を作れたというか。結果的に性別や年齢、立場の様々な垣根を超えて、どんどん仲間が増えていきました。
映画制作で試みる壮大な社会実験
ー映画「逆光」で主演兼監督を務めてみて、どのような気付きがありましたか?
スタッフのやっていることがよく見えるようになりましたね。これまでは、スタッフの方が今何の仕事をしていて、何を思っているのかよく理解できなかったので、どこか怯えながら現場に臨んでいました。「逆光」で監督としてスタッフ一人ひとりとコミュニケーションをとって、各スタッフがどういう思いで作品に向き合ってるか知ることができたのは本当に良い経験になりました。
ー主演と監督の両立って体力的にも精神的にもかなりハードですよね。
そうですね。役者として演技に入る直前まで、監督として各スタッフや役者とコミュケーション取って現場を整えた直後に、カメラが回れば自分も演技して、それをすぐにモニターまで見に行ってチェックして....。とにかくやることがめちゃくちゃ多い。本来2人でこなす作業を1人でやるとなると時間はかかりますが、でもメリットはすごくあると思います。各スタッフとの信頼関係が築きやすいし、現場の熱量も自分がキープできる。大変でしたけど、僕にとってはすごくやりやすい現場でした。
ー監督を経験したことで、役者としての変化は感じていますか?
今までは「上手く芝居しなきゃ」「別の人間になりきらなければいけない」と頭で考え過ぎて芝居をしていたんですよね。人からどう見られているか気にし過ぎた結果、気付けば八方塞がりな状態に自分で追い込んでいた。監督として自分の芝居を見た時、自意識に囚われたこんな芝居は求めてないなと俯瞰して分析することができて。監督を経験して、視野が広がったように思います。
ー役者としても成長できた。
僕、すごく不器用な役者なんですよね。演出を受けたらすぐにそれを形にできるタイプじゃなくて。「どうすればこの作品はもっと面白くなるだろう」とちゃんと作品に向き合えている状態であればできるんですが、スタッフの顔色を窺って自分の演技が人からどう見えているかで頭がいっぱいになると、途端に演技が下手くそになってしまう。

ー表現者と制作サイド、双方の立場を理解しているからこそ、より完成度の高いクリエイションを追求できた?
現場で同じような思いをしている若手をよく見かけていたので、自分が主導権を握れる現場があれば、自分も俳優のことも楽にしてあげれるなって、ずっと思っていたんですよね。今回の作品では、役者自身の演出を役者目線でしてあげられたんじゃないかと思っています。もちろん至らない部分や、荒削りな部分はあったとは思うんですが。
ー役者だからこそ気付ける点ですね。
あとは、役者が良い作り手と出会える架け橋になりたいという思いがあって。自分にとってあやさんという素敵な作り手に出会えたことが、表現者として前進できるきっかけとなったので。どんなに良い役者でも、世間的に相手にされていない人間って残念ながらたくさんいるんですよね。
僕自身、業界が長いわけではないので批判するつもりはないですが、今の映画業界はお金にならない作品は作らないっていう風潮が強いように感じます。ビジネスとしての成功を追求した映画と、純粋に芸術作品としてクリエイションを追い求めた映画、二極化している印象。良い役者が良い作品に出る機会、良い役者を発掘する場所、それらが今の映画業界には不足しているのではないでしょうか。
ー須藤監督が「映画」というコンテンツを通して届けたいことは、どのようなことですか?
「社会を良い方向に大きく転換させていく」ということを目標にやっています。創作や表現の力で社会に変化を起こすことが出来るということを実感できてる人ってあまりいないと思うんですけど、自分たちの世代がそれを意識することってすごく大事なんだろうなと考えていて。僕が作る映画が、人の能動性を喚起させることで、結果的に社会に彩りを与えることができたらいいなと思っています。
約3年前に出会った「ワンダーウォール」は直球で社会問題を描いた作品で、この作品を通じて社会に変化が起きてほしいと、強く思ったんです。でも、それはそんなに簡単なことじゃないんだと、作品を届けていくうちに分かってきました。作品としては良い評価を得られたけど、社会を大きく変えることは出来なかったなと。そこから、「社会に変化を起こす作品とはどういうことなんだろう」と考えるようになりました。今もまだ模索している段階ですが、「逆光」はその思考の先で生まれた作品です。
映画「逆光」で引き出す若者たちの熱量と能動性

映画「逆光」ポスターヴィジュアル ©︎2021『逆光』FILM
ー映画「逆光」では舞台となった尾道から配給・宣伝活動をスタート。様々な議題について話し合う対話イベント「Dialogue」をはじめ、音楽イベント、ライブ配信、展示会の開催など、観客と作り手の垣根を超えた取り組みが印象的でした。
人の能動性をいかに正しく引き出せるか、それが「社会に変化を起こす」ために重要な方法の一つだと考えています。焦らせたり、痛めつけて能動性を喚起するのではなくて、僕たちの熱量を介して誰かの能動性を喚起させる。それってお互いにとってすごく良いことだし、素晴らしいことだと思うんです。
ー撮影では住民の方がエキストラで参加されるなど、尾道の街全体を巻き込んだ壮大なプロジェクトとなりました。
そうですね、尾道の街をまるっと巻き込んで映画を作ることができたという意味では、壮大な実験だったのかなと思います。広島市の「マウント コーヒー」さんとコラボしてコーヒーを淹れて街を練り歩いたり、古本屋「弐拾dB」さんに劇中で使う小道具の古本を選書してもらったり、尾道では僕たちが思っていた以上に、本当に多くの方に協力して頂くことができて。ありがたいことに、気付いたらかなり大掛かりなプロジェクトになっていました(笑)。
ー街全体に「逆光」チームの熱量が波及していったんですね。
能動的に熱量持って動いている時こそ、人って魅力的に見えるし、ポテンシャルが発揮されるんだなと気付かされましたね。そういう時にこそ社会に変化が生じていくと思うんです。
ー「逆光」の説明し過ぎない台詞回しと情景描写は、観客に自発的な思考を促す機会を与える余白のようなものを感じました。能動性の喚起という部分に紐づいているのでしょうか。
そうですね。あやさんに出会えたことが僕にとっての能動性の喚起だったんですけど、それを自分が作る作品でやれないかなと思っていて。これは自分たちの作品なんだと、観た人に感じて頂けたらすごく嬉しいです。そして劇場の外では、都内のさまざまな場所で「東京尾道化計画」を着々と進めています。
ー「東京尾道化計画」というのは?
「映画的熱空間」と題して、尾道の街全体が「逆光」に染まったあの夏の熱量、そして尾道で自分たちが感じ取ったものを、東京の人々にも届けたい。映画という創作物を媒介とした、ある意味社会運動のようなイメージです。東京では、対話イベント「Dialogue」や、六本木 蔦屋書店でのポスター展など、さまざまな試みを行っています。
ー東京での公開後の反響はいかがですか?
先行公開した尾道は、自分の知らない人しかいない地でしたし、皆さん温かく迎えてくれたので、撮影から公開まで全力でやり通すことができたんですが、東京に戻ってきたら、自分が思っていた以上に自意識が膨らんじゃって、「東京で公開したら失敗するかもしれない」と一瞬怯えてたんですよね。試写会の上映終了後、会場がすごい熱気に包まれているのを見れたことは、自分にとってすごく自信に繋がりました。
ー試写会には、若いクリエイターを中心に招待したそうですね。
普通は業界関係者をメインに招待するんですが、今回は僕らが見に来て欲しいと思った表現者の方達を中心に声をかけました。「逆光」を見て何かしら感じ取って帰ってくれたら良いなっていう思いがあって。








「逆光」劇中シーン ©2021『逆光』FILM
>>次のページは
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【インタビュー・対談】の過去記事
RELATED ARTICLE
関連記事
READ ALSO