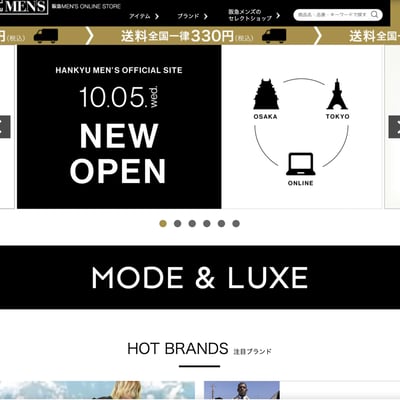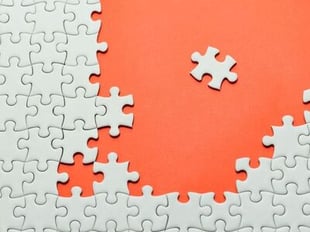顧客がストレスなく買い物を楽しめる環境作りへ

OMO(オンラインとオフラインの融合)という言葉を生んだデジタル先進国の中国ではすでに、そんなワードを持ち出すことはなく当たり前になっているというのを聞いたのは3年ほど前のこと。日本の小売業では概念は広がったものの、なかなか進まなかった。それでも長いコロナ禍を経てようやく販売の現場にまで浸透した1年だった。
ADVERTISING
■実店舗の再定義
実店舗で素材やサイズ感を直接確かめてからECで購入する「ショールーミング」が広がったのは15年ごろのこと。販売員が接客しても、「購入はオンラインで」という消費行動は実店舗とECの対立構造を生んだ。17年ごろからはO2O(ネットと店舗の相互送客)の概念が共有され、18年ごろからはOMOという言葉が広がった。
O2OとOMOの違いは実は大きい。前者は各チャネルを「区別」し、それぞれどう連携させて販売につなげるかという「企業視点」だが、後者は接客から商品の購入、アフターフォローまで、オンラインとオフラインを区別なく「融合」して、より良い顧客体験を提供するかを問う「顧客視点」の戦略だからだ。「どこで買うのも客の自由」だが、実際にOMOなるものが稼働するにはまだ時間を要した。
大きなきっかけは20年春から始まったコロナ禍だ。実店舗の営業機会が失われる一方、ECは大きく伸びた。店に出られない販売スタッフは接客の場をオンライン上に移し、〝1対n〟の接客に勤しんだ。21年は実店舗もやや回復傾向を示す一方で、EC売り上げは足踏みした。
ECの成長が鈍化する中で改めて注目したのが実店舗だ。店舗を再定義し、オンラインとオフラインを行き来する消費者がストレスなく買い物できる環境整備に本腰を入れ始めた。成長するECと実店舗を結ぶ仕組み作りを急がないと、自由に買い場を選べる消費者に追いつけないからだ。
■アパレルで47%
そんな中、22年に一気に広がったのがBOPIS。ECで購入し、店頭で受け取るサービスだ。実店舗の営業に不安がなくなる中で、専門店チェーンを中心に広がった。ショールーミングとは逆にECから店舗に送客する仕組みといえ、店舗での「ついで買い」も期待できる。21年9月にNECなどが実施した日本におけるBOPISの利用状況調査によると、消費者の約3割が今後利用していきたいと考え、アパレルに関しては約47%の消費者が希望。その後、BOPISを実装する企業が急増していることから割合はさらに高まっていることが予想される。
要望が高まるBOPISの課題は店頭のオペレーション整備。店舗スタッフはコロナ下で増え今も続くオンライン接客やソーシャルメディアでの情報発信など業務が過多になっている。あるべき荷姿を店頭でどう整えるか、本社側でも一時的に増える傾向にある在庫をいかに適正化するかなど、解決すべき問題は残っている。
(繊研新聞本紙22年12月15日付)
ADVERTISING
PAST ARTICLES